産学連携先:大阪水上バス株式会社
2年生のゼミでは「都市型観光マネジメントのサポート」をテーマに活動を行ってきました。活動の前半は地域の音楽イベントサポート(報告済み)、後半は大阪水上バス株式会社との共同研究でした。ここでは後半の活動について報告いたします。
大阪水上バス株式会社は、大阪の大川を運航するアクアライナー、大阪港を運航するサンタマリアを代表とする、大阪でアーバンクルーズをビジネスとする京阪グループの企業です。2023年度から清水ゼミで連携をお願いしており、本年度も2つのグループに分かれてアクアライナーについて学び、課題を見つけ、解決に向けての提案をいたしました。実際に何度か乗船させていただき、また議論も重ねながら、2025年2月18日に研究の最終報告をいたしました。結果として、学生の研究を評価してくださり、その課題をさらに深めて再度提案させていただくという機会をいただきましたので、来年度3年生になりますが、継続して研究する予定です。以下は参加学生の活動レポートです。
2年生のゼミでは「都市型観光マネジメントのサポート」をテーマに活動を行ってきました。活動の前半は地域の音楽イベントサポート(報告済み)、後半は大阪水上バス株式会社との共同研究でした。ここでは後半の活動について報告いたします。
大阪水上バス株式会社は、大阪の大川を運航するアクアライナー、大阪港を運航するサンタマリアを代表とする、大阪でアーバンクルーズをビジネスとする京阪グループの企業です。2023年度から清水ゼミで連携をお願いしており、本年度も2つのグループに分かれてアクアライナーについて学び、課題を見つけ、解決に向けての提案をいたしました。実際に何度か乗船させていただき、また議論も重ねながら、2025年2月18日に研究の最終報告をいたしました。結果として、学生の研究を評価してくださり、その課題をさらに深めて再度提案させていただくという機会をいただきましたので、来年度3年生になりますが、継続して研究する予定です。以下は参加学生の活動レポートです。
(国際学部 国際観光学科 教授 清水 苗穂子)
学生活動状況報告
■国際観光学部2年 清水 毅琉
「成果を出せた研究報告」
「成果を出せた研究報告」
私たちは、2024年11月頃から大阪水上バス様を研究し、企画の提案を行いました。研究するにあたって、事前に水上バス様の概要を調査しました。ホームページやSNS、またGoogleの口コミも調査しました。
特にGoogleの口コミ調査では、直近の口コミの評価が低いことが分かりました。なぜ低いかという原因を推測すると、大阪水上バス様は2024年から一周コースの時間を40分から55分へと変更したこと、八軒家浜船着き場の復活による大阪城と八軒家浜を結ぶ片道コースが設定され、プランが改定されました。その改定により評価が低くなっているのではないかと推測し、原因を探るため実際に乗船させていただきました。
最初に、企画担当部の松本さんから話を伺い、大阪周遊パスの特典を利用して乗船している人が半数以上であること、八軒家浜での乗降を増やすことが現状の課題にあると伺いました。そして実際に乗船すると、アナウンスに課題があるように見受けられました。全ての箇所で4か国語放送されていたものの、一部は簡略化されており、またスポット通過後に放送が流れるという課題を発見しました。
しかし、良い面もありました。それは、大阪城と八軒家浜(天満橋)間の移動手段に利用できることでした。そこで私たちは、アナウンスを改善する「アナウンスチーム」と、大阪水上バスが移動手段として利用できることを大阪周遊パス利用者にPRする「PRチーム」という2つに分かれ、研究を進め、私は「PRチーム」を担当しました。
大阪周遊パス利用者がパスの特典のみを目的にせず、移動手段として利用できるというメリットがあることを強調するにはどうしたら良いか考え、パワーポイントにまとめ2025年2月、大阪水上バス様に研究の報告を行いました。
どうしたら魅力が伝わるか、PRの方法は何があるか等をチームで話し合い、スライド枚数は40枚にも及びました。提案させていただいたPR方法として、大阪水上バス様のパンフレットと株式会社するっと関西様のモデルコースを活用し、それらに電車と比較した移動手段を掲載することを提案させて頂きました。報告を終えると、ありがたいことに大阪水上バス様から好評を得て、継続の案件を頂きました。
初めての研究ということもあり、最初は不安と緊張もありましたが良い成果を出すことができて良い学びを経験することができました。
この経験を引き続きの研究にも活かせるように頑張りたいと思います。引き続きよろしくお願いいたします。
この経験を引き続きの研究にも活かせるように頑張りたいと思います。引き続きよろしくお願いいたします。
■国際観光学部2年 杉野 斗夢
「はじめての研究と発表をして」
「はじめての研究と発表をして」
私たちは2月18日に11月から研究を行ってきた大阪水上バスの研究発表をしました。研究するにあたって現状の問題点を把握するために、Googleや旅行サイトでの口コミを調査しました。そこから主にPRと大阪水上バスが所有する「アクアライナー」での船内アナウンスが問題だとし、2つのチームに分かれることにしました。
私はPR担当になり、何かをPRする大変さを物すごく感じました。ターゲットはどこなのか、そのためにそのような内容のものが適しているのかなど挙げていくときりがないことがたくさんでした。その為研究がなかなかうまく進みませんでした。ですが、「アクアライナー」を「移動手段として知ってもらうためには」という考えになったときに、他の交通機関と比較しようとなりました。ほかにも従来のモデルコースは古いため新しいコースの提案をしようともなりました。そうすると、なかなか進まなかった研究が進みだしました。そこから、「アクアライナー」が持つ強みを知りこのことを大阪水上バス様に知ってもらうために、パワーポイントを作成しました。モデルコースも移動手段として知ってもらうようなものにし、自分自身納得のいく内容で初めてにしてはいいものができました。発表後の先方からのコメントでは、「ほかの交通手段との比較、モデルコースのリニューアル、今までしたかったことをしてくれている、よく調べてくれている」とお褒めの言葉をもらいました。ですが、「モデルコースに店の場所を挙げていればなお良かった」というご指導をいただき、次回以降の改善に生かそうと思いました。
今回会社様の研究をするという初めての体験、ゼロから何かを生み出す大変さなど学びがたくさんあった研究であり、大きく成長ができたと感じました。この学び、経験を次回の研究に役立てていきたいです。
■国際観光学部2年 大賀 結太 今回の大阪水上バス「アクアライナー」の報告会では、PRチームとアナウンスチームに分かれて、調査や研究の報告を行いました。PRチームでは、大阪水上バスをどのように移動手段としてPRするのかを考え、アナウンスチームはどのようにしたらもっとお客様に楽しんでもらえるのかを考えました。僕の担当はアナウンスチームで、どのような情報が必要なのか、どの情報が必要ないかをチームで考えました。また、何ヵ国語で放送するかや、ここだけは見てほしいところを多言語で放送するなど様々な視点で考えました。今回の研究を通して、お客様にどのような情報を車内アナウンスで提供すればいいのかを考えることができました。今後も大阪水上バスの研究をしていきたいと思っています。
■国際観光学部2年 大畑 安規 今回水上バスについて2つのチームに分かれてフィードワークをし、報告会にはアナウンスチームとして参加しました。アナウンスチームは元々あるアナウンスの日本語の文考え直し、英語や韓国語、中国語の改正作業を行いました。初めに水上バスに乗った時はアナウンスのないところは退屈に感じることもありましたが、2回目に乗った時はアナウンスの内容をしっかりと把握していたので、外の景色を見ながら楽しむことができました。しかし、外国人観光客はしっかりとアナウンスの内容を理解して楽しめているのかと言われると、表情を見た限りそこまで楽しめていない様子だったので、日本人も外国人観光客も楽しめるようにすることが重要であると気付けました。何回もフィールドワークを重ねることで、毎回違う発見があることを知ることもできました。これらのことを活かして引き続き水上バスをより良いものにするために活動したいと思いました。

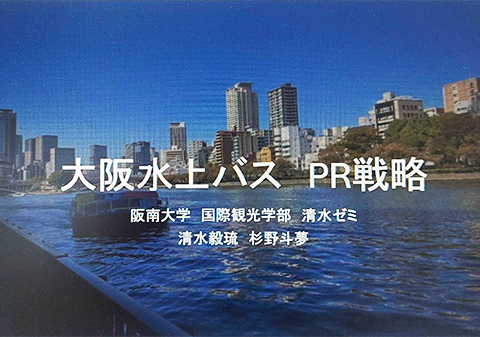
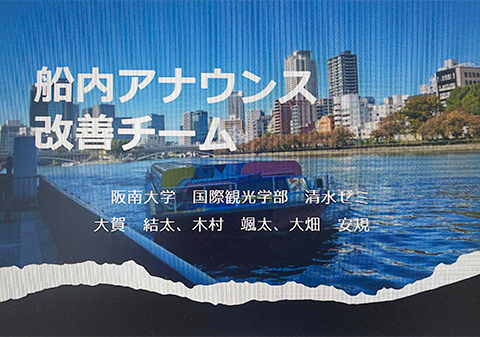

連携先コメント
大阪水上バス株式会社
事業部 企画宣伝担当 松本 珠貴 様
はじめに、昨年に続き2度目のコレボレーションのお話をいただいたこと、この場を借りてお礼申し上げます。
今年は、弊社が運航する観光船「アクアライナー」で、約4年ぶりに八軒家浜船着場への寄港が復活した年でございましたので、八軒家浜船着場からの乗船者数をさらに増やす方法を中心に学生のみなさまに考えていただきました。
PRチームと船内アナウンスチーム、2つのチームに分かれて研究をしていただき、どちらの発表も、改めて弊社のクルーズの魅力に気づかせてくれる内容であると同時に、まだまだ打ち出せていなかった点を発見する報告となっており、私自身も非常に勉強になりました。
今回しっかり研究していただいたので、内容をさらにブラッシュアップさせて、弊社の営業活動に取り込んでいきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
今年は、弊社が運航する観光船「アクアライナー」で、約4年ぶりに八軒家浜船着場への寄港が復活した年でございましたので、八軒家浜船着場からの乗船者数をさらに増やす方法を中心に学生のみなさまに考えていただきました。
PRチームと船内アナウンスチーム、2つのチームに分かれて研究をしていただき、どちらの発表も、改めて弊社のクルーズの魅力に気づかせてくれる内容であると同時に、まだまだ打ち出せていなかった点を発見する報告となっており、私自身も非常に勉強になりました。
今回しっかり研究していただいたので、内容をさらにブラッシュアップさせて、弊社の営業活動に取り込んでいきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。








