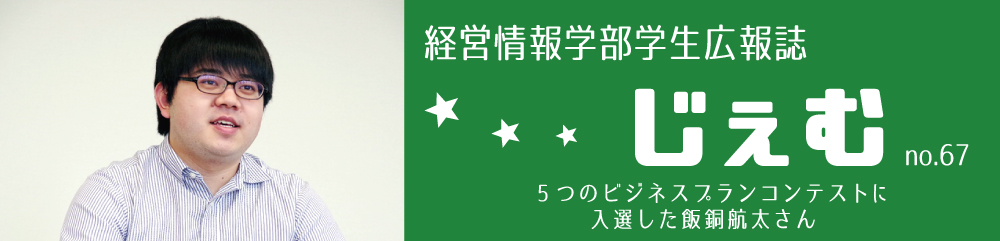文:三戸 一輝 撮影:松本 淳志
今回は、2024年度に5つのビジネスプランコンテストで入賞された、経営情報学部4回生の飯銅航太(はんどうこうた)さんにインタビューさせていただきました。飯銅さんは学生広報委員会の委員長でもあります。
5つのビジネスプランコンテストで入選
——:まずは、「第三回 学生ビジネスプランコンテスト O-BUCs」「関西NBCニュービジネスアワード2024ビジネスプラン部門」「ミライノピッチ 学生の部」「第26回キャンパスベンチャーグランプリ 大阪大会」「テクノ愛2024」での入選おめでとうございます。
飯銅:ありがとうございます
——:それぞれ、どのような賞を受賞したか教えてください。
飯銅:「第3回 学生ビジネスプランコンテスト O-BUCs」では「夢賞」を受賞しました。また、「関西NBCニュービジネスアワード2024」では、ビジネスプラン部門においてグランプリ・オーディエンス賞・最優秀賞を受賞し、企業も含めた関西一位の評価をいただきました。さらに、「ミライノピッチ」学生の部ではNVIDIA賞・株式会社HBD賞・OIH賞を受賞。「CVG(キャンパスベンチャーグランプリ)」第26回 大阪大会では優秀賞と中小企業基盤整備機構近畿本部長賞を受賞。「テクノ愛2024」では健闘賞を受賞しました。
——:受賞されたコンテストの中から「関西NBC」と「キャンパスベンチャーグランプリ」についてお尋ねしたいと思います。
まず、「関西NBCニュービジネスアワード2024 ビジネスプラン部門」についてお聞きします。このコンテストはどのようなものですか?
飯銅:関西ニュービジネス協議会が主催する、企業や団体を問わず応募できるビジネスプランコンテストです。
——:審査方法について教えてください。
飯銅:一次選考の書類審査、二次選考のプレゼン審査を経て、部門賞が決定されます。その中から、最終的に1チームがグランプリに選ばれる仕組みです。
——:一次選考には何チームがエントリーしていましたか?
飯銅:11チームです。
——:二次選考には何チームが進みましたか?
飯銅:他のチームの発表は聞けない形式だったため、具体的なチーム数はわかりません。
——:最終プレゼンはどこで行ったのですか?
飯銅:梅田の茶屋町プラザでやりました
——:プレゼン時間は何分ですか?
飯銅:2次選考はプレゼン時間が5分、質疑応答が5分の合計10分、最終は動画1分説明1分の合計2分行いました
——:企業チームも含めた多くの参加チームの中で、北川ゼミの学生チームが最優秀賞を受賞できた理由は何でしょうか?
飯銅:講評の際に、ビジネスの規模の大きさを評価していただいたので、それが賞の大きな要因だったと思います。
——:次に、第26回キャンパスベンチャーグランプリ 大阪大会についてお尋ねします。こちらはどういったコンテストなのですか?
飯銅:日刊工業新聞が主催するコンテストで、学生同士が競い合うコンテストです。
——:審査方法について教えてください
飯銅:一次選考の書類審査と二次選考のプレゼン選考を行い最終選考のプレゼンで受賞者が決まります
——:一次選考では何チームがエントリーしていましたか?
飯銅:92チームです
——:二次選考には何チームが進みましたか?
飯銅:20チームです
——:最終選考は何チームが進みましたか?
飯銅:8チームです
——:他の受賞者はどんな大学のチームですか?
飯銅:京都大学、神戸大学、奈良先端科学技術大学院大学、立命館大学、同志社大学、京都産業大学、大阪経済大学です。
——:受賞チームには難関大学や有名大学が並ぶ中で、阪南大学の飯銅さんたちのチームが入賞できた理由は何でしょうか?
飯銅:複数のコンテストへの参加を通じてプランをブラッシュアップし、実際にニーズがあるかどうかを重視して分析を行ったことが大きな要因だと考えています。
リベンジを果たすため4回生でもビジネスプランコンテストに挑戦
——:ここからは、ビジネスプランコンテストへの取り組みについてお伺いします。ビジネスプランコンテストにはどのくらいの期間取り組まれましたか?
飯銅:4月から10月の約6か月間取り組みました。
——:北川ゼミでは3回生でビジネスプランコンテストに挑戦するようですが、飯銅さんが4回生で取り組んだ理由を教えてください。
飯銅:3回生の時にもコンテストに参加したのですが、思うような成果を上げることができませんでした。そのため、4回生ではリベンジを果たすために再挑戦しました。
——:チームのメンバー構成を教えてください。
飯銅:大学院生の藤田さん、平山君、学部生の大庭君、そして私の4人でチームを組みました。
ライター注:藤田佑衣子さんは学生広報委員です
——:大学院生をチームに加えた理由は何ですか?
飯銅:前回入賞できなかった経験を持つメンバーを中心に、リベンジを果たしたいという意欲のある人たちでチームを結成しました。
——:飯銅さんのチームでの役割は何でしたか?
飯銅:書類の作成やプレゼンテーションなど、幅広い業務に携わりました。
——:チーム運営の中で困ったことはありましたか?
飯銅:初期のアイデア出しの段階で、なかなか方向性が定まらず苦労しました。
——:どのようにして解決しましたか?
飯銅:とにかく数多くのアイデアを出し、それらを精査することで、最終的に良いプランを絞り込むことができました。
——:全部でいくつのコンテストに応募されましたか?
飯銅: 9つのコンテストに応募し、そのうち5つで受賞しました。
——:半数以上受賞するとはすごいですね!
コンテストによって代表者が違う理由を教えてください。
飯銅:それぞれのコンテストの代表者はあみだくじで決めており、代表者がプレゼンテーションも兼任する形をとっていました。
——:応募するコンテストはどのように決めていますか?
飯銅:昨年参加したコンテストの傾向を参考にしたり、ビジネスプランコンテストを徹底的にリサーチして適したものを選んでいます。
——:ビジネスプランコンテストで入賞するためのコツはありますか?
飯銅:自分たちのアイデアだけに固執せず、客観的に市場のニーズを考えることが重要だと思います。
警備員の巡回業務支援システム
——:続いて、取り組んでこられたプランの内容についてお尋ねします。コンテストに応募したテーマを教えてください。
飯銅:「警備護衛門(けいびごえもん) ~VPS ·AR· Al・画像処理技術を活用した巡回警備補助システム~」です。
——:プランの概要を教えてください。
飯銅:本プランは、ARグラスやモバイル端末、VPS測位技術を活用して警備員の巡回業務を支援するシステムです。警備員がARグラスやモバイル端末を利用することで、業務の効率化と精度向上を図り、人手不足や能力格差、人為的ミスといった課題を解決することを目的としています。
ライター注:ARグラスとは、現実の風景にデジタル情報を重ねて表示するメガネ型のデバイスです。VPS測位技術とは、画像データの情報を利用して位置を特定するシステムのことで、GPS測位技術に比べて電波が届きにくい場所でも正確な位置情報の取得が可能です。
——:このプランはどのような場面で役立ちますか?
飯銅:本プランは、特に警備員が行う戸締りの確認業務の効率化に役立ちます。VPS測位技術を活用することで、警備対象の正確な位置を把握し、確認漏れを防ぐことができます。
——:このプランはどのような議論を経て生まれたのですか?
飯銅:VPS技術について先生の助言を受け、その技術を活用する方法を検討する中で生まれました。シーズ(技術の種)からニーズ(社会的な需要)を考えるプロセスを重視し、警備業務の現場における課題に着目しました。また、阪南大学の警備員さんにもお話を伺い、現場の声も参考にして考えました。
——:プランを考えるうえで苦労した点を教えてください。
飯銅:シーズからニーズを導き出すことに時間を要しました。また、導き出したニーズに対してどのようなアプローチが最適かを検討する際に、さまざまな選択肢を比較しながら試行錯誤しました。
——:コンテストの中で、他の参加者との交流はありましたか?
飯銅:はい、ありました。
——: 他の参加者とはどのような話をしましたか?
飯銅:起業を考えるならどのようなプランが良いか、自分たちのビジネスプランのブラッシュアップについて意見を交わしました。
——: 他のチームのプレゼンを見て学んだことはありますか?
飯銅:参加者の中には、自分のプランに自信を持ち、熱くなったことで、審査員であるベンチャーキャピタルの意見と対立する場面もありました。その経験を通じて、他者の意見を柔軟に取り入れることの大切さを学びました。また、すでに起業している方々のプレゼンからは、自分たちにはない視点を補うことの重要性を実感しました。
——: ビジネスプランコンテストに参加することで学んだことや、自分が成長できたと感じたことは何ですか?
飯銅:多角的な視点を持つことの重要性を学びました。自分では客観的に考えているつもりでも、実際には主観的だったことが多いと気づかされました。ベンチャーキャピタルの方々から「もっと広い視点で考えるべきだ」というアドバイスをいただき、視野を広げることの大切さを実感しました。
——: ビジネスプランコンテストに参加して良かったと思うことは何ですか?
飯銅:普段の生活では得られない貴重な経験ができたことです。また、予測できない質問に即座に対応する力(アドリブ力)を鍛えることができた点も、大きな収穫でした。
——: 今後、ビジネスプランコンテストに挑戦する後輩へのメッセージをお願いします。
飯銅:自分たちだけで考え込まず、受賞経験のある方や専門家など、さまざまな視点を持つ人の意見を積極的に聞いてみて欲しいです。

学生広報委員としてオリンピック選手を取材
——:次に学生広報委員会についてお尋ねします。
学生広報委員会はどのような活動をする組織ですか?
飯銅:学生広報委員会の主な活動は、学生広報誌「じぇむ」の発行で、優れた実績を収めた方への取材記事を作成して大学ウェブサイトに掲載して貰っています。また、オープンキャンパスでは、ブースを出して、取材した方の写真パネルを展示したり、ビラ配りを行ったりしています。
——: 広報委員会にはいつ入られましたか?
飯銅:大学1回生の後期から参加しました。
——: 広報委員会に入ろうと思った理由を教えてください。
飯銅:何か新しい経験を積みたいと考えていた時に、濱先生に広報委員会を紹介されたことがきっかけです。
——: 広報委員会では何を担当されていましたか?
飯銅:主にライターとして記事を執筆していますが、カメラマンとして写真撮影も担当していました。
——: 広報委員会ではどのような研修を行っていますか?
飯銅:ライターとカメラマンに分かれて研修を行います。ライターは模擬記事の執筆を通じて取材の仕方や記事の書き方を学び、カメラマンは撮影技術について実際にカメラで撮影しながら研修を受けます。
——: コロナ禍での活動ではどんな困難がありましたか?
飯銅:行動制限によって大学から取材を差し止められたことがありましたし、屋内での取材が禁止されて真冬に屋外で取材をしなければならないこともありました。また、昼食を食べながらの編集会議ができなかったり、常にマスクを着用していたため、相手の表情を読み取るのが難しい場面が多くありました。
——: 飯銅君の広報委員会での役割について教えてください。
飯銅:委員長を務めていました。
——: 委員長は具体的にどのような仕事をされていますか?
飯銅:編集会議前の先生との打ち合わせ、歓送迎会の企画・運営、ライター研修の講師、LINEグループの管理など、多岐にわたる業務を担当しました。
——: 委員長として大変だったことがあれば教えてください。
飯銅:人に教えることが得意ではないため、研修などで適切に指導できるか不安を感じることがありました。
——: 今まで執筆された記事の中で、印象に残っているものはありますか?
飯銅:三戸一輝さんの記事です。去年は僕がライターを行い取材対象者が三戸さんだったのに対して、今回は反対のインタビューの構図になっているので、印象に残っています(笑)。
——: 昨年、ライターとしてビジネスプランコンテスト受賞者に取材されたと思いますが、その経験が今年に活かされたことはありますか?
飯銅:受賞者の取り組み方やプレゼンの工夫について詳しく伺えたことで、自分自身がコンテストに挑戦する際の参考になりました。また、模擬プレゼンのフィードバックをいただけたことで、より効果的なプレゼンの構成や伝え方を意識するようになりました。
——: 広報委員会の活動を通して、身についたことや成長できたと感じることはありますか?
飯銅:論理的で伝わりやすい文章を書くことを意識するようになりました。また、人と話す機会が増え、コミュニケーション能力も向上したと感じています。
——: 広報委員会に入ってよかったことは何ですか?
飯銅:文章力や取材スキルが向上したことはもちろん、普段ではなかなか話す機会のない方々と交流できたことです。特に、オリンピック選手に取材する機会があったのは貴重な経験でした。

入試成績上位者対象の給付型奨学金制度に惹かれて阪南大学に入学
——:最後に飯銅さん自身についてお尋ねします。 出身高校を教えてください。
飯銅:兵庫県立伊丹高等学校です。
——: 高校時代はどのようなことに力を入れていましたか?
飯銅:部活動と生徒会に力を入れていました。部活動では放送部に所属し、生徒会では厚生委員という学校の清掃関係の委員に所属していました。
——: 放送部で学んだことを教えてください。
飯銅:NHKの全国放送大会に出場する機会が多くありましたが、自分が伝えたいことが必ずしも正しく伝わるわけではないと気づきました。相手に分かりやすく伝えることの難しさを学びました。
——: 生徒会で学んだことを教えてください。
飯銅:生徒会では、厚生委員会の副委員長として活動しました。人数が多いほど、1つの行事を実施することの難しさを実感しました。また、意見をまとめて反映させることの大変さや、人をまとめる上で頭ごなしに否定するのではなく、柔軟に対応することの重要性を学びました。
——: 大学の入試区分を教えてください。
飯銅:一般入試の3教科型(国語・英語・社会)で受験しました。
——:経営情報学部を志望された理由を教えてください。
飯銅:高校時代から情報系の学部に興味があり、その分野を学べる大学を志望していました。
——:一般入試だと他にも大学を受験されたと思いますが、阪南大学に入学した理由を教えてください。
飯銅:もっと上の大学にも合格していたのですが、阪南大学には、入試成績の上位10人が授業料が免除となる制度があって、その対象だったからです。学費免除を維持するために努力し続けられる環境が魅力的でした。
——: 大学で履修してよかったと思う科目は何ですか?
飯銅:北川先生の担当するプログラミングの授業です。この授業がきっかけで、プログラミングに興味を持ち、さらに学びを深めたいと思うようになりました。
——: 広報委員会以外に参加していた課外活動はありますか?
飯銅:学生オリエンテーション委員会にも参加していました。
——: オリエンテーション委員会ではどのようなことを担当していましたか?
飯銅:主に広報を担当していました。特に、新学部の設立にあたり、先生方の紹介をSNSを通じて発信する役割を担っていました。
——: オリエンテーション委員会に入ってよかったことは何ですか?
飯銅:オリエンテーション委員会を通じて、多くの仲間と出会えたことです。学年を超えた「縦のつながり」や、同期との「横のつながり」を築くことができ、とても貴重な経験になりました。
——:所属ゼミを教えてください
飯銅:北川ゼミです
—— 北川ゼミを選んだ理由を教えてください。
飯銅:北川先生の教え方が分かりやすく、主体的に学ぼうとする意欲があればどんどん知識を深められる環境だと感じたからです。
——: 卒業論文のテーマを教えてください。
飯銅:「AR(拡張現実)を用いた3Dデータの描画手法や位置合わせに関する研究」です。具体的には、MMS(モバイルマッピングシステム)で取得した3次元データをAR上に表示する手法の開発に取り組みました。
——: 卒業後の進路は決まっていますか?
飯銅:阪南大学大学院に進学する予定です。
——: 大学院に進学する理由を教えてください。
飯銅:学部卒よりも大学院で専門的な知識やスキルを身につけることで、より高度な分野で活躍できると考えたからです。また、将来的な進路の選択肢を広げるためにも、大学院での研究を深めたいと思いました。
——: 大学院ではどのような研究を行う予定ですか?
飯銅:知覚情報処理を活用したプロジェクトに取り組む予定です。具体的には、現在の研究を引き継ぎ、ARを用いた3Dデータの描画手法や位置合わせの技術をさらに発展させることを目指しています。

取材後記
ビジネスプランコンテストの受賞、おめでとうございます!私たちが昨年受賞したのに続き、後輩の皆さんも素晴らしい成果を収められ、とても誇らしく思います(笑)。また、昨年のインタビューでは私が取材を受ける立場でしたが、今回は逆の立場となり、不思議な感覚を味わいながらも楽しく取材させていただきました。
今後のさらなるご活躍を期待しています!
飯銅さんは面白い方で、歓送迎会で司会を務められる際もちょっとした言葉選びでくすっと笑わせてくださるユーモアあふれる委員長です。この度そんなあこがれの先輩について、詳しくお話を伺えたことが光栄です。
取材の中で「自分がつたえているつもりのことが、相手に届いているのか」という言葉がとても心に深く刺さりました。その場で取材写真の撮り方を考え直し、「自分が思うここぞというタイミングばかり狙うと同じような絵面しか得られない」ことに気づけました。
取材を受けていただき誠にありがとうございました。
今後のさらなるご活躍を期待しています!
三戸一輝
飯銅さんは面白い方で、歓送迎会で司会を務められる際もちょっとした言葉選びでくすっと笑わせてくださるユーモアあふれる委員長です。この度そんなあこがれの先輩について、詳しくお話を伺えたことが光栄です。
取材の中で「自分がつたえているつもりのことが、相手に届いているのか」という言葉がとても心に深く刺さりました。その場で取材写真の撮り方を考え直し、「自分が思うここぞというタイミングばかり狙うと同じような絵面しか得られない」ことに気づけました。
取材を受けていただき誠にありがとうございました。
松本 淳志
ゼミ指導教員コメント
総合情報学部・経営情報学部 北川悦司
まず、多くのコンテストでの受賞おめでとうございます。今まで北川ゼミで20年近くビジネスプランコンテストに挑戦し多くの賞を受賞してきましたが、1年で5つのコンテストで受賞したチームは初めてです。本当によく頑張ったと思います。
飯銅君は、ビジネスプランコンテストの挑戦以外にも、企業との様々なプロジェクトに参加し、ARや画像処理、3次元処理などの最先端技術を利用した多くのシステムを開発してきました。そして、ARのプロジェクトでは特許出願まで達成しました。
大学院への進学が決まっており、今後のより一層の成長に期待しています。
飯銅君は、ビジネスプランコンテストの挑戦以外にも、企業との様々なプロジェクトに参加し、ARや画像処理、3次元処理などの最先端技術を利用した多くのシステムを開発してきました。そして、ARのプロジェクトでは特許出願まで達成しました。
大学院への進学が決まっており、今後のより一層の成長に期待しています。
学生広報委員会担当教員コメント
総合情報学部・経営情報学部 濵 道生
飯銅君が学生広報委員会に入ったのはコロナ禍の真っ最中で、本当に困難な時期でしたね。
飯銅君は学生広報員会の歴史の中で、初の男子の委員長でした。飯銅君は、口数は少ないですが気配り上手な委員長で、とても助けられました。
大学院進学後も広報委員としての活躍を期待しています。
飯銅君は学生広報員会の歴史の中で、初の男子の委員長でした。飯銅君は、口数は少ないですが気配り上手な委員長で、とても助けられました。
大学院進学後も広報委員としての活躍を期待しています。
学生広報委員会では、「じぇむ」の記事を書いていただける方・撮影をしていただける方(総合情報学部生)を募集しています。興味のある方は担当教員(濱、中條)か、教務課までお問い合わせください。