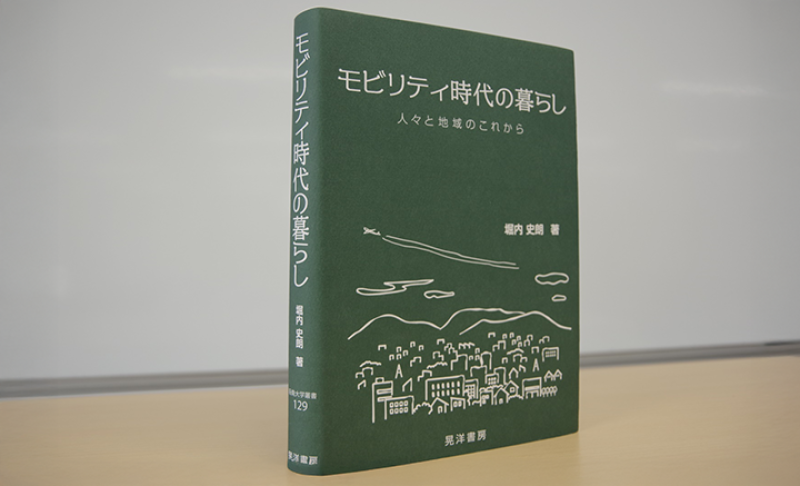文:飯銅航太 撮影:永山華音
今回は阪南大学総合情報学部の堀内教授の著書から「モビリティ時代の暮らし-人々と地域のこれから-」(晃洋書房,2024年)について取材させていただきました。堀内先生の著書の紹介は初めてになるため、堀内先生の経歴やご専門の数理社会学についても伺いました。
所属する集団が移り変わる時代
——:初めに「モビリティ時代の暮らし-人々と地域のこれから-」についてお伺いします。まず「モビリティ時代」とはどういった時代のことでしょうか?
堀内:昔は、多くの人たちがある地域で生まれ、その場所に家族や親戚がおり、その地域または、その近くで進学や仕事、家庭を持ちやがて死んでいくといった、他の場所への転居や転職といった移動が少ない時代でした。しかし近年、終身雇用の制度が無くなり、転職も珍しいことではなく、生涯独身の人が増えたことで自由に移動することが可能になりました。また、会社や友人関係といった所属する集団も移り変わっていくことが増えました。そういったことを総称して「モビリティ時代」と呼んでいます。
——:「モビリティ」という言葉は先生が作られたのですか?
堀内:「モビリティ」といった言葉を作って社会学に応用したのがジョン・アーリという人物です。
——:では、「モビリティ時代の暮らし」とはどういった暮らしのことを指すのですか?
堀内:人の移動が自由になった結果として、生涯独身の人は家族との縁が薄くなり、転職を繰り返し自分が所属する会社への意識も薄くなります。頻繁に引っ越しなどを行っていると常日頃会える友人も少なくなってしまい、人々はどんどん不安になり孤立を深めてしまいます。そのような不安が募る中でどのように人々が互いのことを大事にし、共存できるのか。その理想的な在り方を「暮らし」という言葉で表現しています。
——:この本のテーマを教えてください。
堀内:日本の東京以外の地方では、モビリティ化が進んだことで起きる人口減少に対してどうしたら持続可能な社会を作ることができ、その地域に住む人たちが幸せになれるかといったことがテーマです。
——:首都圏という人口の多い場所ではなく地方といった地域社会に目を向けた本なのですね。堀内先生がこの本を書かれた問題意識は何でしょうか?
堀内:地方から首都圏への移住などが進み、人が少なかった地域がより人口の減少が進むことにより、地域の中小企業の働き手が少なくなることや、公共交通機関の減少など生活が成り立たなくなるといったことが発生しています。人々の移動が活発になった結果として現状の生活を維持できなくなっています。また、若い人が楽しく暮らせる地域をどうやったら残すことが出来るのかといった問題意識を今も持ち続けています。
コンピュータ内に人工社会を構成しシミュレーション
——:この本の5章などで登場しているABM(エージェント・ベース・モデル)とは何ですか?
堀内:コンピュータの中で人工社会を構成し、簡単な方程式を用いて各要素の自律的な行動とその相互作用を何百回、何千回と繰り返しシミュレーションすることで実験を行うことを言います。これを使用するうえで数学の知識だけでなくコンピュータの知識や、統計学の知識なども必要になってきます。
——:難しい内容ですね、私たちの生活の中でABMが関わっている事象はありますか?
堀内:それはもういっぱいあります(笑)。人体の細胞の動きや、生態学や動物行動学の分野における動物の行動予測にも使われます。皆さんの記憶に新しいものでいえば、covid-19(いわゆる新型コロナウィルス)の感染予測にも使用されています。その他にも災害避難、渋滞緩和、テロ対策といった幅広い分野でABMは使われています。
——:この本は書き下ろしですか?
堀内:この本は基本的にこれまで書いてきた論文をまとめてきたものになります。その中で論文のどの部分を一緒にできるか、どうやったら読みやすいかといった章立てや、ABM・統計・社会調査が本の中に全体的に入るように意識しました。また、研究者の人は1つの方法論で研究をする人が多いですが、私は特定の方法論にこだわらず様々な研究手法を取り入れようと心がけています。
——:一つに偏るのではなく満遍なく行うことを意識されているのですね。
この本を書く際に工夫したことを教えてください。
堀内:私の本は文章は難しく感じますが、内容は個別の方法について半年も勉強すれば理解し自分でも実施できる内容です。論文などは基本的に学術雑誌などに掲載されているため一般の方は絶対に読みません(笑)。ただそれを本にして読んでもらうことで、研究者じゃなくても、誰でも研究が出来るということを読者に伝えたいですね。大学院博士課程まで進まなくても研究はできるんだということを伝えていきたいです。
——:この本で使用された論文はどのくらいの歳月をかけられて作成したのですか?
堀内:論文においては査読というプロセスがあるので、だいたい1つの論文ができるまでに短いもので1年ほど、長いものでは調査なども含めて4年ほどの時間をかけています。
——: 4年もの時間をかけられた上で誰でも研究ができるというような内容に落とし込んでいるとはすごいですね(笑)。
堀内:た、確かに、少し矛盾してしまっているかもしれませんね(笑)。
——:検証を行うにあたり大変だったことや苦労したことはありますか?
堀内:現地調査を行う上で人間関係が重要になってくるので現地の方に信用してもらうまでが大変でしたね。ほかにも実験を行う上での目的を見失ってしまわないようにすることや、最新の研究を確認しておかなければ自分の研究を位置づけられなくなってしまう点で苦労しました。
——:この本を書いてよかったことは何ですか?
堀内:「点と線」ですね。これまで個別に書いてきた論文は点なんです。私自身研究者として生涯追い続けたいテーマがあるのですが、個別の論文を書いている際に忘れてしまうことがあります。ただ、本を作成するうえで自分がここ数年間何をしてきたのかそれを線にすることでまとめることができたのは自分にとってのプラスだと思います。あとは、研究のおもしろさを伝え、研究を促すことができる点が良かったと思います。
京都大学理学部で生態学や数理生物学を学ぶ
——:ここからは堀内先生自身のことについてお伺いします。先生は京都大学理学部を卒業されており、理学部には数学・物理学・化学等の分野があると思いますが、大学の学部生時代にはどのような勉強をされていたのですか?
堀内:まず、京都大学理学部は学科がなく、理学科のみになります。しかし、理学部に入学してから、私は自分が興味があるのは人間社会だと言うことに気がつきました(笑)。その中で、動物行動学や生態学、数理生物学を主に勉強していました。加えて、社会学の勉強や生物学の実習で屋外観察や解剖などをしていました。
——:大学の学部時代の所属研究室を教えて下さい。
堀内:研究室の配属はなかったですね。
——:卒論のテーマを教えて下さい
堀内:「クモのセクシャルカニバリズムについて」です。クモやカマキリはオスよりもメスの方が大きく、交尾期のメスがオスのことを餌と勘違いして食べてしまうセクシャルカニバリズムが起こっています。それについて文献を調べて起こる種と起こらない種に分類し、数理モデルを作成して説明するといったことをしていました。
——:学部時代や高校時代に課外活動などはされていましたか?
堀内:同じ先生に卒論を見てもらっている学生同士で自主ゼミをやっていました。自主ゼミでの勉強会の方が、大学時代の勉強の面でいえば大きかったなと思います。
——:その他、学生時代に印象に残っているエピソードはありますか?
堀内:海外旅行ですね。昔は円高だったこともあり、物価の安い国にバックパッカーのような形で1泊200円とかの場所に泊まるなど印象に残っています。
——:すごいですね、道中でアクシデントなどはなかったんでしょうか?
堀内:暴力事件などの重大なアクシデントなどはなかったですね。現地の人にぼったくられたぐらいです(笑)。
——:ぼったくられはしたんですね(笑)。
続いて京都大学理学部を卒業した後の進路について教えてください。
堀内:京都大学大学院理学研究科において修士、博士の学位を取得しました。
——:大学院に進学することはいつ頃から考えておられましたか?
堀内:大学に入った時点で研究者になりたいと思っていたのですが、分野までは考えていなかったです。人間に関する研究をするために生物を専攻しようと思ったのは3年生のおわり頃です。
——:大学院入試の試験科目を教えてください。
堀内:筆記試験は英語と生物学で、生物学は8問くらいある中から4問選択するといった形式だったと思います.それと面接です。
——:大学院入試の受験勉強はいつ頃から始めましたか?
堀内:本格的に始めたのは4年生に入ってからです。
——:大学院入試の受験勉強は一日何時間くらいやっておられましたか?
堀内:毎日何時間というよりは、集中しているときはとことんやって、集中できないときはあまりやらないみたいな感じでしたね。

屋久島でメスザルに求愛された
——:大学院ではどのような研究をされていたのですか?
堀内:大学院修士の時はシロアリについての研究をしていました。博士課程では研究室を変えて研究をしていました。
——:研究室を変えられたのはなぜですか?
堀内:シロアリをやっていたところで人間について分かるわけないじゃないかと、そんな当たり前なことに修士の時に気づきました(笑)。
——:修士の時にシロアリについての論文まで出されたのにですか?(笑)。
堀内:はい、今振り返っても自分はバカだったなと思います(笑)。それで博士の研究は変更しようと思って霊長類の研究を専門にしている研究室にいきました。教授が西田利貞先生、助教授として後に京大総長になる山極壽一先生がいた研究室です。ただ、そこでは数学を教えてくれないので独学で勉強していました。
担当教員注:助教授は現在の准教授
——:なるほど、そういう背景があったのですね、博士課程ではどのようなことをされていたのですか?
堀内:博士課程の1、2年の時は、屋久島で1年の半分ほどニホンザルを追っかけていましたね。3年生の時は青森県の下北半島に行ってそこでニホンザルを追っかけていました。それで屋久島と下北半島のニホンザルの比較を行ってその違いを行動観察して、統計分析と数理モデルにすることに取り組んでいました。
——:本当にサルを追っかけて日本を縦断されていたのですね(笑)。それでは博士論文のテーマを教えてください。
堀内:「野生ニホンザルのオス達の共存戦術」です。
——:1年のうちの半分をサルと過ごされていたと思うのですが、慣れてもらうためにはどれくらいの期間がかかるのですか?
堀内:だいたい1か月もあれば十分だと思います。また、観察に行ったところは比較的人に慣れているサルだったので、近づくと威嚇はしてきますが、堂々としていたら敵でも味方でもないと許容してくれるようになりました。
——:観察するうえで大変だったことはありましたか?
堀内:屋久島で記録を取っているときにサルが後ろから近づいてきて頭髪の毛づくろいをされた時はびっくりしましたね(笑)。
——:毛づくろいですか?(笑)。仲間に間違えられたんでしょうか?
堀内:そういうわけではなく、そのメスザルが発情期だったため誰彼構わず求愛行動していたので、僕に寄ってきました(笑)。
——:(笑)
堀内:他には、サルはこちらに合わせくれないため朝から晩まで動き回るので体力的にもしんどかったですし、特定の場所にいるわけではないのでサルが見つからずに一日が終わることもありました。
——:その後阪南大学で先生をされるまでの経歴を教えてください。
堀内:大学院を修了後すぐに先生になる人もいますが、私自身は動物学のポストがあまりなかったため、3年間や5年間の任期ごとに移動することを繰り返していました。行く場所ごとに任期の間に論文を書き続けなければいけなかったり、場所に合わせてテーマを変えたりなど大変でした。
——:堀内先生は京都大学でサルの研究で学位を取られたということですが、観光学の授業を担当されているのはどういった経緯でしょうか?
堀内:ニホンザルの研究で学位をとった後、人間の研究をしようと思いました。ただいきなり人間だと広すぎるので、サルつながりで、サル害を被っている住民とサル、そしてサルを追い払うためにやってくる「サル追い上げボランティア」の関係についての研究をしていました。そこではエアガンを用いてサル追い上げを市として許可した結果、サバゲーマーの人たちが集まってきたんです(笑)。
——:エアガンを山で撃つことができる貴重な機会だからですかね(笑)。
堀内:サバゲーマーの方々にも地域の人々を助けたい気持ちはあったと思いますが、それにしては迷彩服を着てきたり顔にフェイスペイントを施したり、サルの通る場所を予測して夜明け前から張り込むなど、サル側からしたら普段は老人しかいないと思っていたら若い人から急に銃で撃たれるなどでびっくりして実際に効果がありました。そこからこれはボランティアでもあるけど、コアな観光だなと感じ、観光の分野について研究を始めました。

専門は数理社会学
——:先生のご専門を教えて下さい
堀内: 数理社会学です。
——:これはどういった学問なのでしょうか?
堀内:社会現象や社会的相互作用を数学的手法を用いて分析する学問です。上で説明したABMや統計、簡単な数学を使います
——:数理社会学でどのようなことがわかるのですか?
堀内:直感や言葉では説明がつかないような、複雑な人間関係や社会の仕組みがわかります。
——:人工知能(AI)やビックデータは数理社会学にも役立つのでしょうか?
堀内:どちらも役立ちます。まずビッグデータは統計分析をする際の素材であるだけでなく、ABMの結果を検証する際にも用いられます。またABMのプログラムを作るときに、私は生成AIをよく使っています。生成AIだけだとエラーになってしまうので、研究者にもプログラムの知識は必要なのですが、マニュアルを確認する手間が省けるので助かっています。
——:総合情報学部での担当科目について教えてください。
堀内:「基礎数学1,2」「数理社会学」「移動の社会学」「多変量解析」です。
——:阪南大学総合情報学部に関心のある高校生にメッセージをお願いします。
堀内:総合情報学部に入ったら、コンピュータを必ず使いますが、その使いかたはさまざまです。いろんな専門を持った先生がいらっしゃって、動画編集とかシステム構築とか金利計算などをされる先生もいます。一方で私のように、調査で得られたデータを統計分析したり、ABMで新しいデータを作ったりする人間もいます。バラバラなようでも、今の世界を少しでも住みやすくしようという点では一致していると思います。大学生にとって一番大切なのは、受け身ではなく、自分から積極的に動くことです。面白い先生を見つけて自分なりに世界を少しでも良くしてほしいです。と言うことを、30年以上前の自分にも言いたいです(笑)。
取材後記
私の取材経験の中で最も内容が濃く楽しい取材をさせていただきました。私自身、大学院進学ということもあり、堀内先生の誰でも研究ができるという言葉に心を打たれ、今後の学生生活をより一層頑張ろうと思うことが出来ました。最後になりましたが、この度は貴重なお時間を割いて取材に応じてくださりありがとうございました。
私は、堀内先生の入門ゼミの学生だったので、取材を担当することができて良かったです!そして、入門ゼミで軽く仰っていた猿の研究について、今回概要を知ることができました。毛繕いの話は初耳で面白かったです。いつも明るく話が面白い堀内先生は、取材中も面白く、こちらも楽しかったです!お忙しい中、取材を受けてくださり、ありがとうございました。
飯銅航太
私は、堀内先生の入門ゼミの学生だったので、取材を担当することができて良かったです!そして、入門ゼミで軽く仰っていた猿の研究について、今回概要を知ることができました。毛繕いの話は初耳で面白かったです。いつも明るく話が面白い堀内先生は、取材中も面白く、こちらも楽しかったです!お忙しい中、取材を受けてくださり、ありがとうございました。
永山華音
学生広報委員会では、「じぇむ」の記事を書いていただける方・撮影をしていただける方(総合情報学部生)を募集しています。興味のある方は担当教員(濱、中條)か、教務課までお問い合わせください。